PTSD・CPTSD・DTD(発達性トラウマ障害)を理解するための基礎と比較
PTSD(心的外傷後ストレス障害)・CPTSD(複雑性PTSD)・DTD(発達性トラウマ障害)
近年、トラウマに関する理解は深まり、新たな診断概念として「Developmental Trauma Disorder(DTD)」が注目されています。
しかし、DTDをしっかり理解するためには、まずPTSDやCPTSDがどのように生まれ、どんな特徴があるのかを知ることが重要です。
この記事では、PTSDの誕生背景から始め、CPTSDとDTDの違いをわかりやすく解説していきます。
PTSD誕生の背景
PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、主に戦争から帰還した兵士たちの症状をもとに作られた診断名です。
彼らが経験した「戦闘体験」という強烈な外傷に対する急性の反応を分析し、フラッシュバックや回避行動、過覚醒などの症状が特徴とされました。
しかし、PTSDはあくまでも「単発の外傷体験」に対する反応を中心に考えられていたため、長期間にわたる慢性的なトラウマには対応しきれない面がありました。
PTSDという病態を最初に体系的に研究し、理論化した重要人物として多くの研究者がいます1が、PTSDという診断名の確立と普及は1970〜80年代にアメリカ精神医学会がDSM-IIIで正式採用したことが大きな転機でした。
CPTSDの登場と特徴
そこで登場したのがCPTSD(複雑性PTSD)です。
CPTSDは、長期間にわたる繰り返しの虐待や人間関係の問題など、複数の慢性的なトラウマ経験に対して考案された診断概念です。
PTSDの症状に加えて、感情のコントロールが難しい、自己イメージが歪む、人間関係がうまく築けないといった特徴も含まれます。
これにより、PTSDの診断範囲が広がり、より多くのトラウマ被害者の苦しみを説明できるようになりました。
CPTSD(複雑性PTSD:Complex PTSD)は、主に精神科医である**Judith L. Herman(ジュディス・L・ハーマン)**が1992年に提唱した概念です。
Developmental Trauma Disorder(DTD)とは?
さらに、子どもや発達段階にある人々に特有のトラウマ影響を示す診断概念として、DTDが提唱されました。
DTDは幼少期の反復的・慢性的なトラウマ体験に着目し、それが心身の発達に及ぼす影響を詳しく示しています。
具体的には、情緒調整の困難や注意欠如、対人関係のトラブル、学習障害などが挙げられ、これらは発達期のトラウマに特有の症状とされています。
CPTSDと似ている部分もありますが、DTDは特に「発達障害的な視点」からトラウマを捉えている点が特徴です。
DTDは、『The Body Keeps the Score(和訳:身体はトラウマを記憶する)』の著者でトラウマ研究の第一人者ベッセル・ヴァン・デア・コークをはじめとする研究者たちが提唱する発達性トラウマの概念。
PTSD・CPTSD・DTDの比較表
| 項目 | PTSD | CPTSD | DTD |
|---|---|---|---|
| 誕生背景 | 戦争帰還兵の急性トラウマ反応に基づく | PTSDの限界を補う形で慢性トラウマに対応 | 幼少期の慢性的トラウマが発達に及ぼす影響に着目 |
| 対象トラウマ | 単一の外傷体験 | 複数・長期間の慢性的トラウマ | 反復的・発達期のトラウマ |
| 主な症状 | フラッシュバック、回避、過覚醒 | PTSD症状+情緒調整困難、自己認識障害 | 情動制御困難、発達障害様症状、対人困難 |
| 対象年齢 | 主に成人 | 成人・青年 | 主に子どもや発達期 |
| 名称 | 主な特徴 | 原因 |
|---|---|---|
| PTSD(心的外傷後ストレス障害) | 命の危険を伴う出来事や強い恐怖体験の後に、フラッシュバック・悪夢・過覚醒などが続く | 災害、事故、暴力、戦争など |
| CPTSD(複雑性PTSD) | PTSD症状に加え、感情調整の難しさ・自己否定感・対人関係の困難が慢性的に続く | 長期的虐待、監禁、家庭内暴力など |
| DTD(発達性トラウマ障害) | 幼少期の繰り返しのトラウマ体験により、発達段階全体に影響 | 虐待、ネグレクト、家庭内混乱など |
まとめ
PTSDはトラウマ理解の第一歩として大きな役割を果たしましたが、その枠組みでは幼少期の慢性的なトラウマを説明しきれません。
CPTSDはそうした慢性的なトラウマに対応するために発展しましたが、発達的な影響への注目はまだ十分とは言えません。
一方、DTDは幼少期のトラウマが心身の発達に深刻な影響を与えることを示し、発達障害的な症状も含めて包括的に捉えようとする新しい概念です。
トラウマ理解の深化により、今後より適切な支援や治療法の開発が期待されています。
自己チェック表
「PTSD」「CPTSD」「DTD」。
どれも“トラウマ”が原因で起こる心の障害ですが、その内容や経過は少しずつ異なります。
- 自分がどの状態に当てはまるのか知りたい
- 適切な治療やセルフケアの方向性を見つけたい
そんな方のために、今回はそれぞれの特徴と見分け方、そして自己チェック表をご用意しました。
以下の質問に、当てはまるものをチェックしてください。複数可。
| 項目 | 私の状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 幼少期に養育者からの虐待・ネグレクト・遺棄があった | 例:暴力、感情的無視、過干渉も含む | |
| トラウマは1回ではなく長期間繰り返された | 例:数ヶ月〜数年単位 | |
| 幼少期から人間関係がうまく築けなかった | 愛着の不安、回避、依存など | |
| 感情が強く揺れやすく、コントロールしづらい | 怒り、恐怖、絶望、恥など | |
| 自分に価値がないと感じる | 「私はダメだ」が常にある | |
| 人との距離感がわからない | 近づきすぎる/避けすぎる | |
| 学習・集中・記憶が苦手 | 幼少期からの傾向 | |
| 身体症状(慢性疲労、痛み、消化不良など)がある | ストレス性身体反応 | |
| トラウマ記憶のフラッシュバックや悪夢がある | PTSD症状 | |
| 日常生活や仕事・学業に大きく支障が出ている | 社会生活への影響 |
結果の目安
- 幼少期からの発達的影響が多い → DTD傾向
- 大人になってからも長期的な対人トラウマが続いた → CPTSD傾向
- 単発の事故や災害後の強い症状 → PTSD傾向
PTSD/CPTSD/DTD比較
| 項目 | PTSD(心的外傷後ストレス障害) | CPTSD(複雑性PTSD) | DTD(発達性トラウマ障害) |
|---|---|---|---|
| 主な原因 | 単発の強い出来事(事故、災害、暴力など) | 長期的・繰り返しの対人トラウマ | 幼少期の慢性的虐待・ネグレクト(特に養育者から) |
| 発症時期 | どの年齢でも | どの年齢でも | 幼少期のみ |
| 症状の中心 | フラッシュバック、悪夢、回避、過覚醒 | PTSD症状+感情調節困難、自己否定、人間関係困難 | CPTSD症状+発達面の遅れや機能障害 |
| 愛着への影響 | 必ずしも影響なし | 不安定な愛着スタイルになりやすい | 愛着障害(混乱型・回避型など) |
| 自己認識 | トラウマ以前の自己感は比較的保たれる | 強い恥や無価値感 | 自己感が未発達・歪んだ形成 |
| 発達への影響 | 基本なし | 基本なし(ただし生活機能低下) | 認知・言語・社会性などに影響 |
| 治療アプローチ | トラウマ処理(EMDR、認知処理療法など) | トラウマ処理+感情調節スキル訓練 | トラウマ処理+発達支援+愛着修復 |
| 診断の有無 | DSM-5 / ICD-11で正式診断 | ICD-11で正式診断 | 未公式(研究・臨床用) |
まとめ
- PTSDは「単発的外傷」で、戦争・社会運動・精神医学の進化が重なって誕生した病名です。
- CPTSDは、数か月〜数年にわたる逃げられない慢性的な対人トラウマを説明するために作られた概念。
長期トラウマ(子ども時代でも大人でも)による大人での最終的な症状像。 - DTDは、必ず幼少期の虐待・ネグレクト・遺棄・慢性的な恐怖が原因。特に養育者が加害者の場合。
子ども時代の段階で現れる形で、脳や人格の発達がトラウマで書き換えられてしまった状態。 - DTDが早期に治療されなければ、成人してからCPTSDとして現れることが多い。
DTDが早期に治療されなければ、成人してからCPTSDとして現れることが多い。
- チャールズ・ホイットン・スティーヴンス(Charles S. Figley)
ピエール・ジャネ(Pierre Janet)(19世紀末〜20世紀初頭の心理学者でトラウマの早期研究者)
ビビアン・コブラー(Vivian Kobler)
ジョン・ボウルビィ(John Bowlby)(愛着理論で有名だがトラウマの研究にも影響) ↩︎
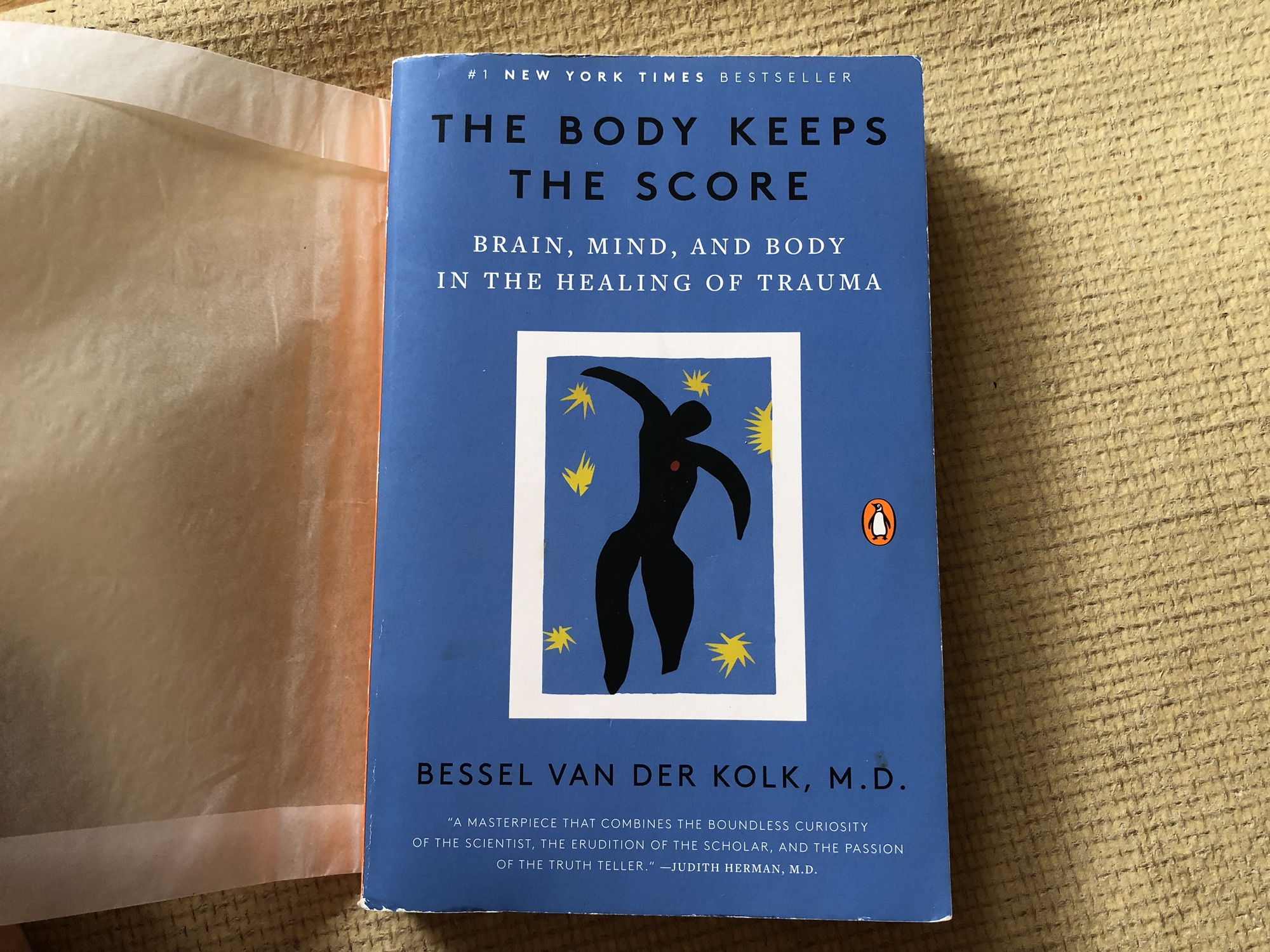
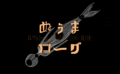
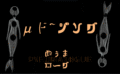
コメント