幼少期のネグレクトや虐待によるトラウマは、大人になっても影響を残す。
発達性トラウマ障害(DTD)
「複雑性PTSD」や「愛着障害」や「発達障害」との違い・症状・治療法・チェックリストなど
🧠⚡️発達性トラウマ障害(DTD)の概要
もしかして——
子どもの頃から、ずっと安心できなかったり、信じられる人がいなかったりしませんでしたか?
そのような環境は、子どもの脳や神経の発達を妨げ、大人になっても心や体の動き方に残ります。これは近年のトラウマ研究で明らかになっています。
発達性トラウマ障害(DTD)は、子どもの頃に繰り返されたつらすぎる経験によって、心や体に強いストレス反応を抱えた状態です。
原因は、虐待や暴力だけではありません。
・放っておかれていた
・信じられる人が誰もいなかった
・安心できる居場所がなかった
こうした不安定・不健全な環境も含まれます。
DTDは、10歳前後くらいまでの幼少期(発達の基盤がつくられる時期)に経験したトラウマが中心です。
大昔から「三つ子の魂百まで」と言われるように、幼い頃に身についた性格や性質は、歳をとっても残るとされています。
現代のトラウマ研究(※)でも、子どもの頃の環境が、脳の発達や心の反応パターンに長く影響することがわかっていますが、
英語で「Developmental Trauma Disorder(DTD)」と呼ばれている発達性トラウマ障害は、
絶望しか知らなかった人が、少しずつでも心の落ち着きを得られるようになるための手がかりを探す研究でもあるのです。

全ては育った環境のせい。
悲しいことに、世界は理不尽で、育った環境に恵まれた人ばかりではありません。
この記事は、この世の中で最も環境に恵まれなかった人たちが、これ以上、自分を責めないように書いています。
無理せず、ゆっくり読み進めてください。
🔍 DTDに特化した症状
🧩発達そのものへの影響
- 自分という感覚が薄い、またはゆらぎやすい
- 安心感という状態がよく分からない
⚡️慢性的な緊張や麻痺
- ずっと緊張している
- 逆に、感覚や感情が鈍くなる
🔄対人関係での「役割」が固定化
- 子どもの頃に担わされた役割(世話役、聞き役、犠牲者など)から抜けられない
- 新しい関係でも同じパターンを繰り返してしまう
🎭感情・行動の“年齢のズレ”
- 大人の場面でも、子どものような反応や感じ方になることがある
- 必要以上に自己批判や罪悪感を抱く
💔自己価値感の低さ
- 無条件に「自分は価値がない」と感じる
- 褒められても肯定的な感情が湧かない
😶🌫️慢性的な解離傾向
- 記憶が抜け落ちていて、断片的
- 体から切り離されたように感じ、現実感が薄れる
🕳“発達の取りこぼし”による困難
- 社会的スキル、自己管理能力、感情表現など、成長過程で学ぶはずのものが欠けている
- 大人になってから学び直しが必要になる

これらの症状はほんの一部です。
DTDは、「複雑性PTSD(CPTSD)」や「愛着障害」、「発達障害」の症状と重なる部分も多いですが、
大きな違いは、**「発症のタイミング」と「発達への影響の深さ」**です。
比較することで、みえてきます。
▲「複雑性PTSD」との違い
複雑性PTSD(CPTSD):
小さい頃から辛い経験が長く続いた人に多く見られますが、思春期以降であっても逃げられない状況が長く続く場合に起こり得ます。
感情コントロールの難しさ、解離(気持ちと体が現実から離れたように感じること)、自己否定感など、DTDと重なる症状も多いですが、
被害が始まった年齢が遅いほど、自分の気持ちや考えをわかる力が備わっているため、回復しやすい傾向があります。
詳しくは ➡ DTDとCPTSDの違い
▲「愛着障害」との違い
愛着障害:
親や養育者からのネグレクトや関係の不安定さによって、安心感や信頼感を学べなかった結果として生じます。
対人関係における行動パターンに注目する点ではDTDと重なりますが、
DTDはさらに、記憶喪失や解離、自己否定感など、脳・心・体を含む個人全体への影響まで視野に入れています。
詳しくは ➡DTDと愛着障害の関係
▲「発達障害」との違い
発達障害(ADHD・自閉スペクトラム等):
生まれつきの特性。トラウマは原因ではないですが、症状が似る部分もあります。
詳しくは ➡DTDと発達障害の違い
💔 DTDは治るのか
「完治」というよりは、症状が少しでも軽くなり、生きやすくなることを目指します。
回復には段階があり、自己理解と支援環境が重要です。
➡ 関連:「治し方・向き合い方」
➡ 関連:「チェックリスト」
❤️🩹 DTDの治し方・向き合い方
- 心理療法(EMDR、ソマティック・エクスペリエンシングなど)
- 身体アプローチ(ヨガ、マインドフルネス、呼吸法)
- 薬物療法(効果の乏しい薬品が多い中、M D M Aがずば抜けて効果的という研究結果が出ていますが、それだけに違法のままです)
➡ 詳しくは「治療法まとめ」
✅ チェックリスト
自己評価ができる簡易シートです。診断ではなく、気づきのためのツールです。
➡ 「発達性トラウマ障害チェックリスト」
📚 DSMやICDでの扱い
- DSMやICDには正式採用されていない理由
- 臨床での扱われ方
- 代替診断名(例:PTSD、解離性障害など)
➡ 「DSMとの関係記事」
💡関連作品
📗名著『身体はトラウマを記憶する』
『身体はトラウマを記録する――脳・心・体のつながりと回復のための手法』
- トラウマ研究の第一人者による著書『The Body Keeps The Score』(2014)が原作
- 幼少期のトラウマが心だけでなく、体にまで影響を及ぼすことを解説
- 心理療法や身体アプローチの手法、M D M Aなどの薬物療法も紹介
- 50年以上の研究を経て、発達性トラウマ障害の概念を世間に広めた名著です
🎞映画『ミステリアス・スキン』
- 機能不全な家庭環境や幼少期の性的搾取・トラウマが、子どもの記憶、セクシャリティ、行動にどうに影響するかを模写
- 思春期以降の人生に与える影響を、子どもの視点から丁寧に模写した珍しい作品(2014年公開)
- 少年期に性被害を経験した著者による小説『Mysterious Skin』が原作

🦉まとめ
発達性トラウマ障害(DTD)は、幼少期から続く深い影響を理解し、適切に向き合うために重要な概念です。
ここで紹介した各テーマを読み進めることで、自分や身近な人の経験を整理し、より生きやすい方向を探るヒントが見つかるはずです。

私は「発達性トラウマ障害(DTD)」という概念を知るまで、自分の症状を「複雑性PTSD(CPTSD)」だと思っていました。
しかし、思春期以降から始まった虐待を含むCPTSDの幅広い枠組みの中では、幼少期から始まった虐待やネグレクトにおける不利の理解がされにくいと感じていました。
あの人は、自分より悲惨な虐待を受けてきたのに、なぜ私の方が回復が遅いんだろう?と悩みました。
でもトラウマの後遺症は、トラウマ体験の悲惨さ以上に、それが何歳から始まったのか、味方になってくれる人はいたのか、という背景やその後のサポートによって回復のスピードが大きく違ってきます。
私はずっと、自分より被害経験が遅くに始まった人や、味方がいた人と自分を比較しては自分はどんな努力が足りないのか悩みました。
一方で、自分より幼い年齢から被害が始まったり、味方が1人もいなかった人は大体、小児性偏執者か連続殺人犯になっていました。
私は加害経験もあるのですが、加害者であることを自覚することは、自分が受けた被害経験よりも苦しいことです。
幼い頃から「正しい」と叩き込まれてきたことが「犯罪」だった。だから加害をしてしまえた。それが「加害である」と知らずに。
発達性トラウマ障害には、幼い頃の被害が、大人になってどう影響するかということが分かりやすくなっています。
共感されやすい生きにくさを抱えることから、誰も理解できない犯罪者になってしまうケースだってあります。
人生への影響は、トラウマの悲惨さだけでは決まらない。
人格形成の時期や、そばにいてくれた人の有無が、大きく左右するのだと。
私たちは、同じ土俵にすら立っていなかったんです。
それに気づいたとき、少しだけ、自分を責めることを手放せました。
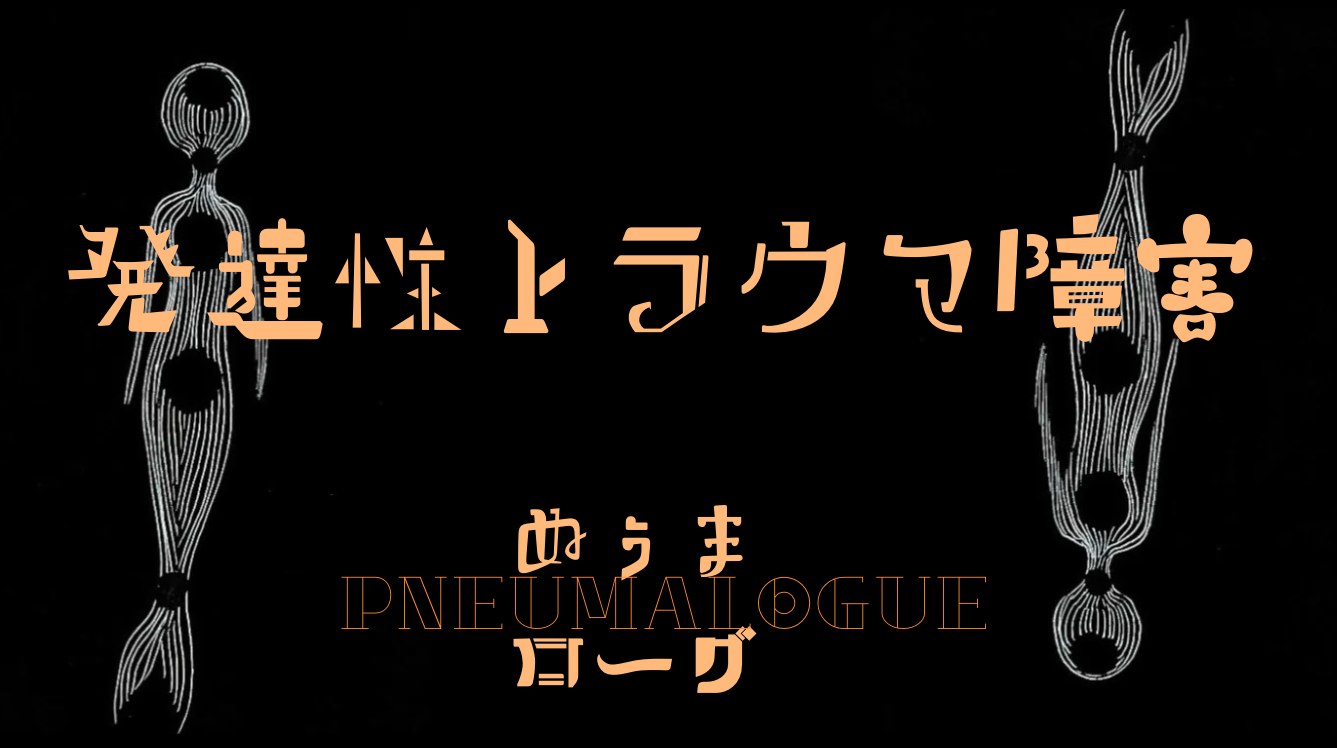
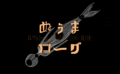
コメント