「出身はどこですか?」
初対面の人に聞かれる質問で、私が苦手とするもののひとつ。
「東京」と答えてテキトーにはぐらかして、話をなるべく広げない工夫をする賢さを身につけられるようにはなったけど、最近まで馬鹿正直に答えては無駄に神経をすり減らしてきた。
「えっ、とー……〇〇〇〇です」
するとお決まりの反応がだいたいこんな感じ。
「え!かっこいいー。ってことは英語ペラペラなんですか?!」
「あ、はい」
「すごーい!」
「ハハハ(笑って誤魔化す)」
「え?ハーフ?帰国子女?」
「いや、二重国籍です」
「すごーい! かっこいー!」
リアクションに困る。間が持たない。消えたい。
(心のため息は独りになってから吐く)
この複雑な心境、私の性格が捻くれてるからなのは百も承知。
だとしても、実は「日系人あるある」なんじゃないかと踏んでいるんだけど、どうなんでしょう。
心当たりある方、コメントで教えてください。
だってさぁ
生まれ育った国の言語を話せるのってフッツーじゃね?
褒めてるつもり?下手かよ。
それに出身地が「かっこいい」ってよく言われるけど、
ナイーブにも程があるでしょ。
「すごーい」のはハリウッドの洗脳力ですから。
なんて、日本語でこういう皮肉をいうイメージあんまないけど、
みんなが必死で目指してる「生きた英会話」は
「ほぼ皮肉で成り立ってる」と言っても過言じゃないので、
悪しからず。
(あ。皮肉で「すごい」とか「かっこいい」と言っている日本語圏の方がいらしたら、一本取られましたね^^ 気が合いそうです)
そもそも私が生まれたのは、
みんながだいたいイメージする「かっこいい」Cityだけど、
育ったのはSuburbですからね。
ジャパニーズでいう郊外の住宅街よ。
退屈だった記憶しかないですわ……。
嘘。楽しいことも稀にあったっけ。
家族ぐるみで付き合いのあった日本人家族と年に一度くらいに会った時とか。
4歳上と6歳上の優しくて美人なおねえちゃんが2人いて、憧れの存在だった。
でもある時期から、色々なことが楽しくなくなっていった。
例えば、私が4歳くらいの頃、2歳下の弟と戯れていた際、弟の頭を壁にぶつけたの。
すると「やめなさい!お姉ちゃんでしょ!」と、険しい顔でおねえちゃんに怒られて、ショックを受けた。
それは私が誤ってやったことではなくて、おねえちゃんから肯定的に注目して欲しくてワザとやったことだったから。
思い返すと、自分の恐ろしさに気づかされる。
この幼い子どもの時点で、私は既に暴力で自分の存在を他人に肯定してもらおうとする手段を見よう見まねで身につけ始めていた。
そして、そのやり方を否定されたのが予想外だったのだ。
当時はまだそんなことに気づくわけもなく、
ショックと不満を埋めるために開き直った。
それまで呼び捨てし合っていた1歳と2歳下の弟達に
「これからはお姉ちゃんと呼んで」と従わせ、
一緒に対等に遊ぶことも減っていった。
それから一年くらい後のこと。
例のおねいちゃん達から無条件に可愛がられる弟たちに混ざって、
無邪気に遊ぶことができなくなっていた私は、
お母さんたちがおしゃべりしているダイニングで会話を聞いていた。
話題はキムタクから、恋愛話に移っていったが、
母は黙って聞いているだけ。
小学1年生くらいになった私はその頃、
同級生の男子に初恋をしていたので、参加したくてうずうずしていた。
そして「あ」と言った瞬間、「大人の話ッ!」
ピシャリと言い放った鬼の目に私は凍りついた。
その場をすぐ離れたものの、居場所がどこにもなくなり、その後、どこで何をしていたのか全く覚えていない。
そういう一年に何回かの特別な日以外は、ほぼ学校と自宅の往復。
母が学校まで迎えにきて、歩いて家に帰る。帰ったら家事の手伝い。
変わり映えのない日々だから大した思い出もない。
そんな日々に耐えられず、ある日の帰り道、私はついに思い切った行動に出た。
母の目を盗んで、道を間違えたふりをして、近所に住む例の初恋の同級生の家に向かったのだ。
偶然、家の前にいた彼が笑顔で私の名前を呼び「Pass me the ball」と言った。
私が持っていたボールを投げると、彼はそれをバウンスして返してきた。
幸せなひととき…..は、一瞬で壊れた。
母親は私を見つけるなり、鬼の形相で怒鳴った。
私は涙を流すものかと食いしばったけど、消えていなくなりたいほど、惨めな思いをしたことは鮮明に覚えている。
「〇〇が教科書、借りにきたみたいよ〜」
その後いつだったか、彼がうちに来たことを知らせる母の呑気な声に苛立ちを感じ、恥ずかしさから私は彼にそっけない態度をとった。
そんな自分が嫌で仕方なかった。
その後も、彼がよく乗っていたgopedが、
我が家の前を通り過ぎる音が聞こえるたびに、苦しくなっていた。
平日通ってた現地校に友達と呼べる人はいなかった。
週一で通っていた日本語学校には2~3年生くらいから女友達が1人できたけど、一緒に遊べるのは土曜日の放課後だけ。
弟たちは2軒隣に住んでいた同級生と家を行き来してゲームをしたりしていたが、私はその男子が大嫌いで睨みつけていた。
私は毎日、家で母の家事の手伝いをして退屈なのに、弟たちと毎日楽しそうに遊んでいるそいつが許せなかった。
私は自由がほしくて、一刻も早く大人になりたいと思った。
大好きだった絵本はほとんど捨ててもらった。
でも、もっと本質的に大人になるには働かないとと思って、
「お父さんの店で、働かせてください!」と10歳の誕生日、
父の足元で土下座をして頼み込んだ。
床に額をつけながら、心がざわついたけど、
時代劇で見た侍の仕草を真似した甲斐はあった。
毎週日曜の朝から夜18時くらいまで店の手伝いをした。
身長が足りないから、レジの真下に箱を置いたりして。
夕方になると客が引いて暇疲れしたけど、家にいるよりマシだった。
確か一日5ドルしか支払われなかったけど、お金のために働いていたわけでもないし、お金があっても自由に使わせてもらえないし、家にいるよりマシだった。
日本語学校の友達が買い物にきた時だけ、身を隠した。
ローラーブレードのままスイスイと入店してお菓子を買っていく同級生の姿が眩しかった。
14歳。法的な労働許可が降りる年齢になると、常連客からすかさずスカウトされ、仕事を引き受けた。
勤務日数は土日祝に増え、拘束時間も朝から深夜までに延びて、
休憩時間もないほど忙しかったけど、
家や父の店にいるより時間を忘れられ、断然充実していた。
ある元旦の深夜、仕事から帰ると、母親が作って置いてくれたおにぎりを一口含んだ途端、涙がツーっと流れて、びっくりした。
食事や休憩の時間がなかったのは当たり前だったけど、
気づかないところでお腹が空いてたことには、
無感情な涙で初めて気づいたのだった。
母は、私が遊びに行くことは渋っても、
バイト時間に制限をかけることは不思議と一度もなかったので、
その抜け穴を最大限に利用しない手はなかった。
しかしバイトのない月曜日から金曜日は相変わらず、母親の手伝い。
でも「飴と鞭」で言うところの「飴」もちゃんとあったから、
正直、さほど苦だとも思っていなかった。
例えば、母は毎年、塩辛を作ったのだが、イカの口(希少部位でトンビという)の唯一無二なコリコリ食感を味わさせてもらえたのは毎回、5人家族で私だけだった。
味見当番としての特権は、私の自尊心を保ち、弟たちに優越感さえ持つことができてていた。
「夕食は一家揃って食べるのが夢だった」という父の意向で、
毎晩7時くらいにみんなで合掌して一斉に元気よく「いただきます!」と言ってから食べるのが日課だった。
食事中、戦後ひもじい想いをした父の話や、
世の中には今も、ご飯が食べられなくて餓死してしまう子供たちが大勢いる話を何度も聞いた。
我が家に居候していた現役バックパッカーのおじさんが見せてくれた一枚の写真も目に焼き付いている。

この子と比べたら、自分は恵まれている。
だから、不満を感じるのは罰当たりだと自分に言い聞かせていた。
八十八の過程を経てご飯になった米粒も箸で寄せ集めて、有り難く頂いた。
両親の手作りご飯は美味しかったし、
「食べさせ甲斐のある娘だ」と、食欲旺盛な私を褒めてくれた。
飲食業を代々営んできた我が家では「食」に関しては唯一、
大人も子供も分け隔たりなく、平等に与えられたいた感覚があり、
私の唯一の誇りであった。
私は、ご飯を何杯も何杯もおかわりして、底なし沼のように食べた。
合掌して元気よく「ごちそうさまでした!」というと、
2階のトイレに駆け込み、
正露丸を飲みながら下痢をするのは毎晩のことだった。
「なんで毎晩、お腹を壊すまで食べてしまうんだろう」
という疑問はよぎったけど、「摂食障害」だとは思えなかった。
なぜなら周りには痩せるために嘔吐する拒食症の例ばかりが話題になっていて、「痩せの大食い」である自分は該当しないと思っていたから。
中2になって、現地校に友達ができた。
放課後、友達の家に行ってお喋りする時間が楽しくてたまらなかった。
でも17時頃、迎えにきた母親の車が見えると、気持ちがズーンと重くなった。
夕食の後は「もう暗いから」という理由で遊びに行かせてもらえなかった。
お泊まりしたいと言っても「この前したばかりでしょ」などと言われて許可がなかなか下りない。
門限を破るようになると、帰るたびに母親から長時間の説教とビンタを食らった。
母親から頬を叩かれる度に、ある映像が脳裏をかすめた。
その映像は、昔からずっと「悪夢だ」と思っていたことなので、信憑性が疑わしい。けど、それが毎回思い出された。
でも、その「悪夢」が仮に事実だったとしても、絶対墓場まで持っていこうという決心が、顔を打たれるほどに強固されていった。


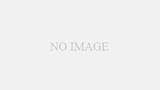
コメント